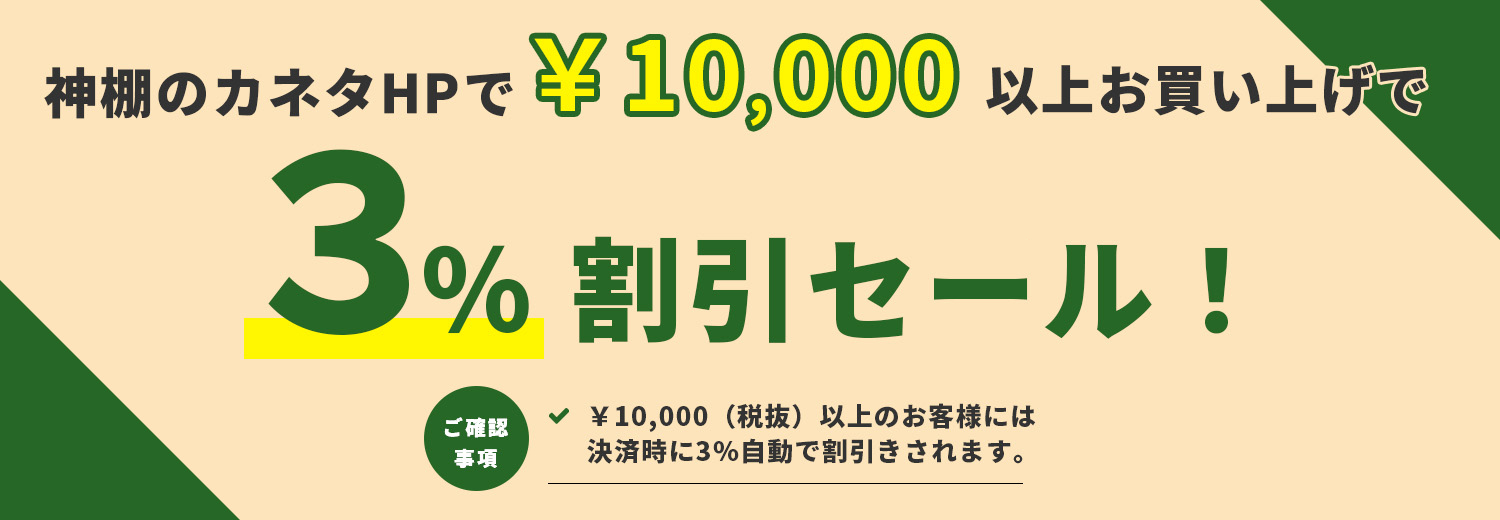お知らせ
| 2024.4.15New | 5月2日~5月6日迄問合せ・出荷作業は、お休みになります。期間中に品物のお届けは、出来ません ので、早めの注文で、指定日も出来ますので、宜しくお願い致します。 |
|---|---|
| 2024.4.9 | 場所など決まりましたら 御宮を迎え入れる前にきれに掃除をしましょ御宮の廻りだけでも 良いので、掃除が、終わりましたら よいよ御宮を置いて御札を入れて 朝一番の御水と洗米・あらしおを お供えして日々の感謝をして 例(昨日は沢山売れましたありがとうございます。)等の日々感謝を込めてお祈りしましょう |
| 2024.3.13 | まずは、神棚・お宮を御向かい入れようと思った所から 始めましょう。その①神棚の場所を決めよう ※基本は、扉の向きが南・東に、お祀りしましょう又頻繁に、 神棚の下を通ったりする所は避けて静かな場所を選びましょう。(冷蔵庫・エアコン・テレビ) 付近を避けると なってますが、現状住宅では、困難でしょう なるべくで良いので リビングなど家族が、集まる所などは、良いと思います。場所が決まったら お祀りする神棚を選びましょう 御札のサイズが、在るので基本は、御札が、見えない様 神棚を選びましょう |
| 2024.2.28 | お部屋に神社様から頂いた御札を そのまま 壁等にお祀りしてませんか?開運を掴むには、 御札立て等を使って 御水・洗米・塩等をお供えして開運をゲットしましょう 詳しくは、次回に |
| 2024.2.13 | 動物のメモリアルハウス 新登場 是非😄見て下さい
|
| 2023.12.10 | ※左側の各種のカテゴリー 一覧の下をクリックしてお買い物を楽しんで下さい |
| 2023.12.7 | 新規! ブリザーブド榊始めました。 ブリザーブド榊は枯れず毎日の水替えの要らない榊です。 |
カネタの神棚
Kaneta's altar

大切なことはお祀りする気持ち
厳選した静岡の「駿河ひのき」から
神棚のための神棚棚板を
丹精込めて制作しています。
おすすめ商品
Recommendation

仏壇特集
Special feature
カネタでは、仏壇・仏具も販売しています。仏壇を購入したいと思った時、何を購入したらいいのか、購入後サイズが合わないなど、初めての方にとって分からないことが多いと思います。
カネタではそんな方のために、仏壇&仏具のセット販売をしています。初めての方でも、簡単にご購入いただくことが可能です。
ご利用ガイド
お支払い方法について
銀行振込・クレジット決済・コンビニ決済・代金引換のうちからお選びください。
クレジット決済については、Amex・ダイナース・JCB・MasterCard・VISAをご利用いただけます。

その他詳細についてはご利用ガイドページをご確認ください。
お届けについて
注文日より5日後~14日後までの日付よりお選びいただけます。
特にご指定がない場合については、ご注文後(代金前払いの場合は弊社にてご入金確認後、3営業日以内※土日・祝日除く)に発送いたします。
お届けについて
配送料は商品のサイズ・配送先住所によって異なります。ご購入前に各商品の配送料をご確認ください。
佐川急便にて配送いたします。
返品・返金について
ご注文された商品と違う商品が届いてしまった場合や、商品の破損・傷みなど品質上の問題があった場合には、以下の手順で返品をお受け致します。
- 商品到着後3日以内に、まずはメールまたはお電話にてお知らせください。
- その後、お手数ですが、着後7日以内にご返品ください。
- 良品との交換をご希望の場合は、代替品を配送いたします。
お問い合わせ
Contact
受付日 / 月~金
受付時間 / 8:30~16:30